鉄骨造より木造が安心?構造計算における安全率の違いを解説
構造計算において同じ荷重条件を与えた場合、鉄骨造よりも木造のほうが安全率に“余裕”があるケースがあります。
特に雪国などの多雪地域では、構造計算による「安全率の設定」が建物の信頼性を大きく左右します。
本記事では、構造計算の基本的な流れに沿って、木造・鉄骨造の安全率の違いを具体的に解説していきます。
このコラムでわかること

構造計算の基本|部材にかかる力(応力)の算定
構造計算では、まず建物にかかる荷重から、各部材に生じる曲げモーメント、せん断力、軸力などを算出します。
多雪地域では5つの荷重ケースを考慮
特に多雪地域では、以下の5つの荷重ケースを想定して検討を行います。
・常時荷重
・積雪荷重
・風荷重
・地震荷重
・その他の荷重(施工条件など)
これらの荷重に対して、どの部材・接合部にどの程度の力がかかるかを詳細に解析するのが、構造計算の第一段階です。
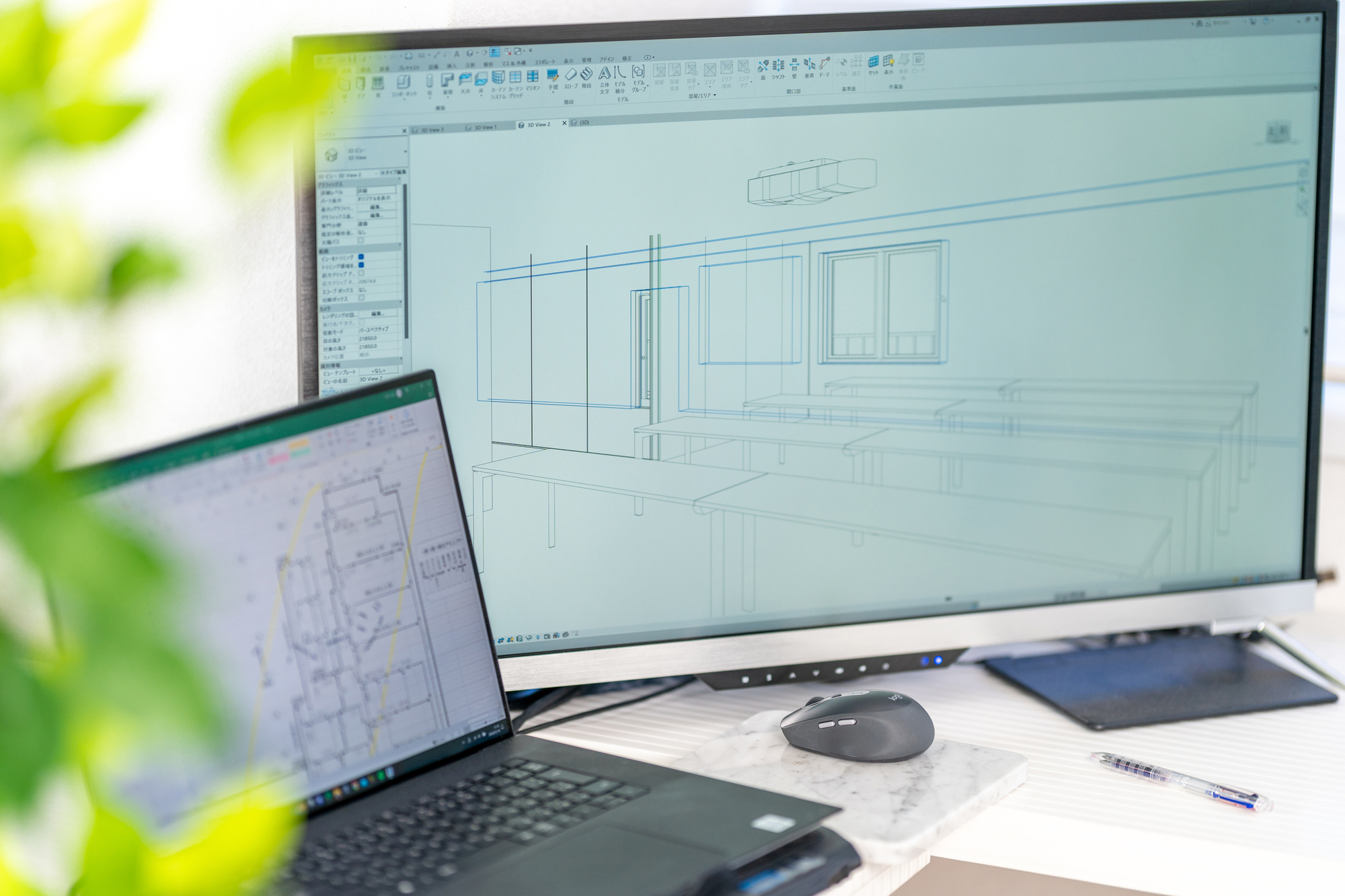
構造部材の安全性をどう判断するか?|許容応力度による検定
F値(基準強度)に対する「安全率」の違い
次に行うのが、各部材が壊れないかどうかを確認する「部材の検定」です。
構造計算では、部材の強度であるF値(基準強度)に対し、どの程度の荷重まで許容されるか(許容応力度)を材料別に設定します。
以下は、常時荷重(長期荷重)に対する代表的な安全率です。
・木造:F値の1.1/3以内
・鉄骨造:F値の2/3以内
・RC造(コンクリート):F値の1/3以内
木材は自然素材ゆえに高い安全率
木材は自然素材のため、強度にばらつきがあるという特性があります。
そのため、安全率が高めに設定されているのが特徴です。
また、長時間荷重がかかることで生じる「クリープ変形」も考慮され、荷重の種類や時間に応じた係数が細かく分かれています。
なお、木造では“構造材に集成材(エンジニアリングウッド)”が多く使われており、これは製材よりも品質が安定しているため、安全率の適用に柔軟性があります。
鉄とコンクリートは工業製品としての扱いに差がある
鉄は品質が安定した工業製品であるため、比較的安全率が低めに設定されています。
一方、コンクリートは現場打ち施工で品質のばらつきが出やすいため、安全率が高めに設計される傾向があります。
接合部の構造設計も、木造では実験に基づく厳格な基準
接合部もF値に基づき安全性を検証
部材と同様に、接合部にかかる力に対しても構造検討が行われます。
木造建築における接合部は、実際に破壊試験などを行ったうえでF値(基準強度)が設定され、構造計算に取り入れられています。
WOODCOREで採用している「MPねじ type-L」なども、こうした基準に基づいて設計されています。

WOODCORE規格トラスの事例で見る「木造の安全率」
トラス1本あたり約15tの荷重に余裕を持って対応
WOODCOREの標準規格トラス(スパン10.01m、ピッチ2.73m、積雪1.5m)の場合、1本あたり約15tの荷重が想定されます。
この荷重に対して、木造ではF値の1.6/3以内に納める必要があります。
一方、鉄骨造はF値以内に収まっていればOKという基準のため、設計時点での余裕度に差が生じます。
まとめ|構造計算では木造のほうが「余裕」をもたせる設計
設計荷重が基準値まで積もるような状況(富山県では積雪1.5m)では、
・木造は安全率に基づいた余裕のある設計
・鉄骨造はギリギリの設計になることも
という違いが明確に出ます。
また、そもそも構造計算をしていない建物では雪の荷重想定が行われていないため、安全性の比較すらできません。
しかし、適切に構造計算を行った上で比較すれば、“木造は鉄骨造よりも「安全マージンが大きい」”というケースも十分にあるのです。
